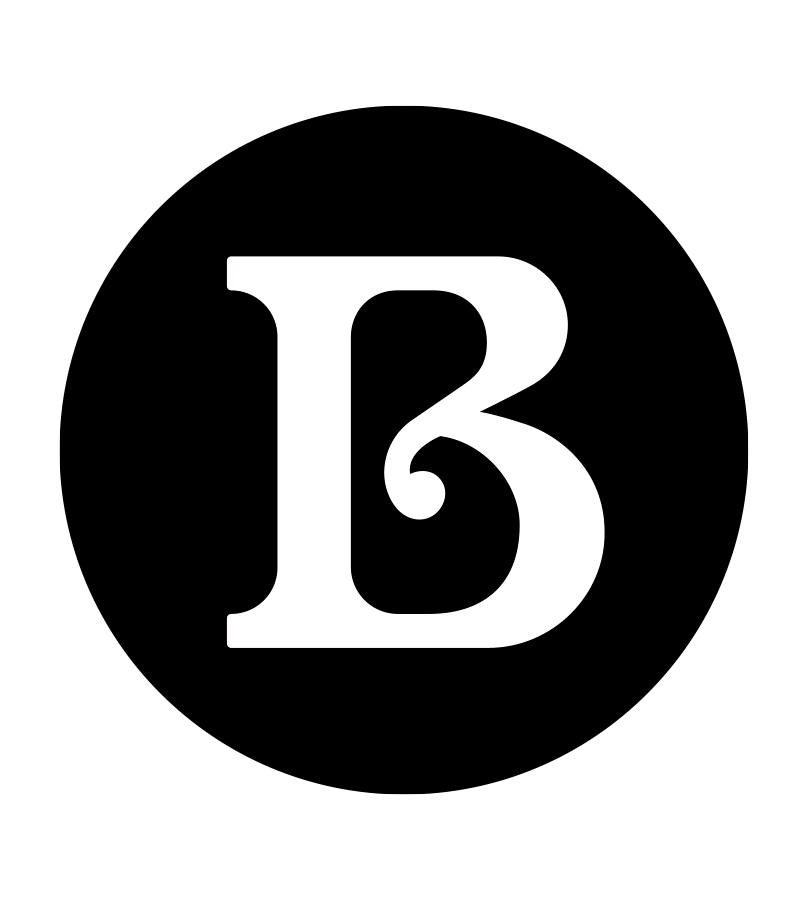“稼ぐ”って聞くと、どうしても肩に力が入ってしまう。ギラギラしていて、なんだか自分とは遠い世界の話みたい。でも、生きていくうえでお金とどう付き合うか? もっとフラットに語っていいはずだ。
今回話を聞いたのは、中三青果店の三代目・山田海斗さん。コロナ禍をきっかけに家業を継ぎ、ただ野菜を売るだけではない「新しい八百屋のかたち」をつくろうとしている。最近は新たに法人を立ち上げ、飲食店のオープンも控えているという。
そんな山田さんのこれまでと、お金の向き合い方を通して、“稼ぐ”ことをもっとリアルに見つめ直してみたい。

山田 海斗
新しい八百屋の姿を提案する中三青果店を運営。その他にもFarmers Marketの企画・運営や、農家さんの販路拡大をサポートするコンサルティングも業務として行う。2025年9月には八百屋がプロデュースする飲食店のオープンを控える。
Instagram:@kaito_yamada
ナカサン青果店:https://nakasan-seikaten.com/
イベントから八百屋へ。表現の場としての中三青果店

──普通の八百屋さんというより、スタイリッシュでびっくりしました。中三青果店は、どんなお店なんですか?
山田:祖父の代から続いていて、僕で三代目になります。もともとは向河原駅の近くに店があったんですけど、地元への思いもあって、1年前に新丸子に移転しました。どちらも川崎市内で、多摩川を越えればすぐ東京。渋谷からも30分くらいで、都心からのアクセスもいいんですよ。


内装は、野菜の色がパッと映えるようにコンクリート打ちっぱなしでシンプルにまとめています。ディスプレイやパッケージ、接客の仕方まで「ここ、なんかいいもの置いてそう」と思ってもらえるように意識しているんです。
野菜は単価が低いので、普通の八百屋さんは量で勝負しがちなんですよね。僕らは、そうじゃない“稼ぎ方”を模索していて、それぞれの野菜の背景や価値をちゃんと伝えたいなと思っています。
たとえば洋服屋さんで服がぐちゃっと積まれていたら、どんなにいい服でも魅力は伝わらないですよね。野菜も同じで、手に取ってじっくり見てもらえる空間づくりが大事だと思っています。

──具体的には、どんな業務をされているんですか?
山田:父と分業していて、地元の保育園などの配達は父が担当で、僕は店舗での販売やイベントの企画、商品開発などを主に担当しています。単に野菜を並べて売るだけでなく、地域とのつながりや新しい提案も含めて、いろんな機能を持っているのが今の中三青果店の特徴だと思います。

──家業を継ぐことになったきっかけを教えてください。
山田:両親からは「継がないほうがいい」と言われていました(笑)。朝はすごく早いし体力もいる。今はスーパーで野菜が手に入るから、わざわざ八百屋で買う人が減っていて、なかなか厳しい商売だよと。でも、僕はずっと「場をつくる」ことに興味があって、気づいたらその延長線上に八百屋があったという感覚なんです。
──「場をつくる」というと……?
山田:大学時代、イベントのオーガナイザーをやっていたんです。音楽やアパレルなど、本気で表現している仲間たちと一緒に何かをつくりあげたくて。音楽と古着、写真の展示をミックスしたイベントからスタートして、atmosさんとコラボしたこともありました。
──その後、どうして青果店の道へ?
山田:やっぱり、コロナの影響が大きかったです。イベントが軒並み中止になって、オンライン開催も試してみたんですが、どうしても物足りなくて。やっぱり自分がやりたいのは、リアルな場づくりなんだなと改めて実感しました。
そんなときに、ふと「実家の八百屋はめちゃくちゃポテンシャルあるんじゃないか?」と思ったんですよね。小さい頃から「うちの野菜は本当にいいんだ」と親から聞かされていたけれど、今なら自分のやり方で良さを伝えられるんじゃないかと。八百屋を、僕なりの表現のフィールドにできるかもしれないと思ったんです。

──そこから新しい解釈の八百屋がスタートしたと。
山田:そもそも八百屋って、八百万の屋。野菜に限らず、雑貨や乾物まで扱う当時のセレクトショップのような存在だった。それなら、自分の表現とも地続きでできるかもしれない。そう思ったんです。
続ける、届けるために稼ぐ
──実際に「八百屋をやる」と決めてからの日々は、どうでしたか?
山田:いやあ……めっちゃ大変でした(笑)。実家でやっていたとはいえ、実際の現場は知らなかったので、まずは修行からスタートしたんです。
いざ「明日からよろしく」と社長である父から始業時間を聞いたら「朝2時50分集合」って。今までだったらその時間まで普通に遊んでたので、聞いた瞬間「マジか」って衝撃でした。

──まさかそんな早朝から……。
山田:そこから市場で仕入れをして、八百屋同士で情報交換して戻ってきたらすぐ店舗の準備。昼から夜までは納品や仕込み勉強などで、ひと息つく暇もない。「八百屋ってこんなに地道で過酷な仕事なんだ」と思い知らされました。
──そういう経験を通して、あらためて感じたことってありますか?
山田:思っていた以上にハードな世界だなって驚いたんですけど、それ以上に「これはめちゃくちゃ尊い仕事なんだ」って気づいたんです。配達先の保育園で園児たちを見かけたとき、「あ、俺らが毎日届けてる野菜って、この子たちの身体をつくってるんだな」ってリアルに感じて。

──野菜の価値の見え方が変わってきたと。
山田:そうですね。最初は「おしゃれに八百屋やれたらいいな」とか「何か新しいことやりたい」っていう思いが強かったけど、だんだんと「これは街にとってちゃんと意味がある仕事なんだ」って感じるようになってきて。そこから、「じゃあ、どうやったらこの仕事をちゃんと続けられるんだろう」って考えるようになりました。
──続けるために“稼ぐ”という視点ですね。
山田:そうですね。野菜って、1個あたりの利益率がすごく低いんです。だから、スーパーでは大量に仕入れて、価格を下げて、たくさん売るという仕組みで利益を出すのが一般的で。
でもそれって、すごく不安定なんですよね。ちょっと値段が上がっただけで「高い」って言われるし、いいものを届けたくても、そのぶんのコストがまかなえない。ああ、ちゃんと“稼ぐ仕組み”を考えなければ、続けていくことはできないんだなと、実感しました。
ただ、だからといって野菜を高級品にしたいわけではなくて。うちでは、できる限り日常使いできる価格で野菜を届けられるように心がけています。そこは創業時からのスタンスでもあるし、僕らの大事にしている部分です。

そのぶん、どうやって価値を感じてもらうかという工夫はすごく大事にしていて。たとえば、うちの「フルーツポンチ」は人工甘味料を使わず、果物そのものの甘みや酸味といった果物の個性で勝負しています。遠方からこれを目当てに来てくれる方もいて、新しいお客さんとの接点にもなっているんです。
ロスが出にくい仕組みにもなるし、単価が高い分しっかり利益も出せる。野菜そのものの敷居は上げすぎずに、お店全体としての収益バランスが保てるんですよね。
山田:祖父の代では店舗販売だけでしたが、父の代からは保育園や飲食店への配達もスタートしました。僕の代では、そこに「選ばれる理由」をちゃんとつけていく。そんな感覚でやっています。「なんでも変えればいい」というわけじゃないし、全部を新しくする必要もない。大事なのは、守るものはちゃんと守りながら、その上で新しい挑戦を仕掛けていくこと。そうしないと、お店って続いていかないと思うんです。
──逆に、うまくいかなかったこともありましたか?
山田:めちゃくちゃあります(笑)。たとえば昔、Tシャツをつくって販売してみたんです。でも、全然売れなかった。アパレルって、むずかしいですね。

商売と表現の間で“稼ぐ”と向き合う
──いろんなチャレンジを経て、少しずつ「中三青果店のあり方」が見えてきたと。
山田:そうですね。最初は「かっこいい八百屋にしたい」とか、自己表現的な部分も大きかったけど、今はもっと続けることに重きを置いています。誰に、何を届けているのか。どうやったらこの仕事が続いていくのか。そういう視点で“稼ぐ”ってことを、ようやく自分ごととして考えられるようになりました。

──そうした考えの延長で、法人も立ち上げられたとか。
山田:実は青果店とは別に、飲食業をメインにFarmers Marketの企画・運営や農家さんのコンサル・プロデュースを行う会社を立ち上げました。中三青果店に来てくれる地元以外のお客さんって、20〜30代の若者が多いんですけど、わざわざ八百屋まで足を運ぶのってハードルが高いじゃないですか。だったら、彼らの目的になるような飲食店をつくれば、より自然に野菜の魅力に触れてもらえるんじゃないかと考えて。
──法人設立の後押しとなった出会いがあるとか。
山田:中学の同級生で、当時から「将来はコンサルになる」と言っていた変わり者がいて。ある日ふらっとお店に遊びに来てくれたんです。実際にコンサル業についていて、「ちょっと手伝ってよ」って軽く声をかけたら、出してくる企画書も数字の分析もめちゃくちゃ鋭くて。「数字で話せる人って、こんなに頼もしいんだ」と本気で驚きましたね。はじめは、正直「コンサルって何する人なんだろう?」って思ってたくらいだったんですけど(笑)。
──そこから一緒に仕事するように?
山田:それまでは「いい感じのビジュアルができたら、とりあえず広告まわしてみよう」みたいなノリだったんですけど、彼と動くようになってからは、「なぜそこにお金を使うのか?」「何をもって成果とするのか?」をちゃんと考えるようになった。自然と“投資的に稼ぐ”っていう視点が育っていった気がします。責任も増えたけど、長く続けていくための仕組みを、一緒に組み立てられる安心感があるんです。

──とはいえ、利益だけを追うわけではないと。
山田:そこは本当にバランスです。ブレたら意味がないから。僕らしいスタイルや信念を守るために、考えて“稼ぐ”ということを意識しています。仲間とやる意味も、まさにそこにあるんですよね。生活のためのライスワークと、自分の表現としてのライフワーク。両方を成り立たせるのは簡単じゃないけれど、だからこそ向き合い続けることが大事なんだと思います。どちらかを諦めるんじゃなくて、「どうしたら両立できるか」をずっと考え続けたいんです。
──そういう理想と現実の狭間で、“稼ぐ”ことを実践してる感じですね。
山田:まさにそうです。家業を続けるのも、農家さんに正当な対価を払うのも、いい野菜を子どもたちに届けるのも、全部お金が必要なんですよ。だからお金と向き合うことから逃げずに、自分たちのやりたいことを実現するためには? 自分たちらしく続けていくには? ということを模索し続けたいんです。そのためにも、“稼ぎ方”に美学を持つということを大事にしていきたいですね。