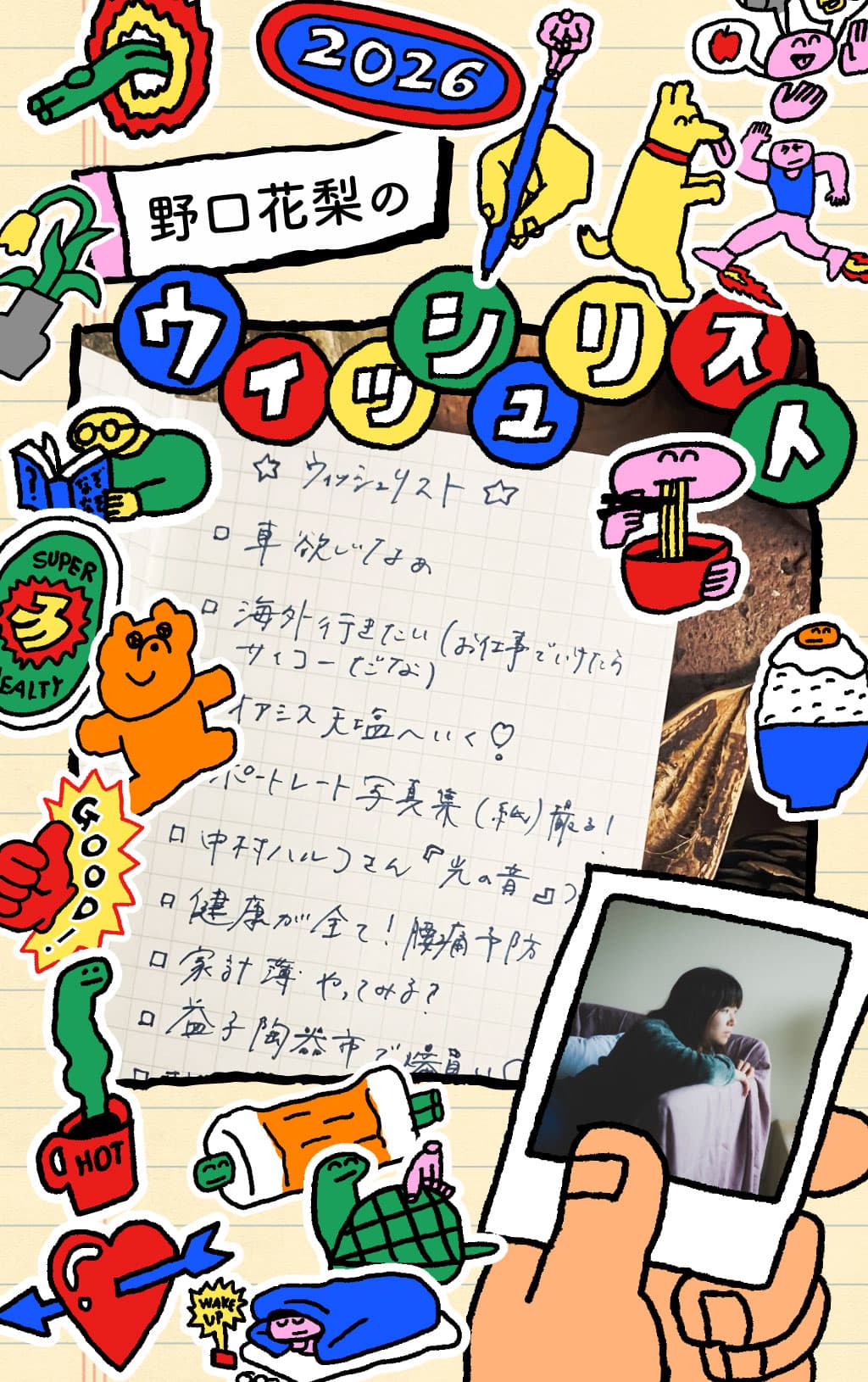2020年、コロナ禍を迎え、デジタル化が遅いと言われていた日本でも、あっという間にリモート会議システムが広まった。「デジタルトランスフォーメーション(DX)」が流行語となり、Eコマースを含むIT系の企業は活況。政府も「今こそ一気にデジタル化」と盛り上がっている。
デジタルトランスフォメーション(DX)の罠

確かにデジタル化が進んだおかげで、満員電車は緩和され、わずか数十分のミーティングのために遠出をすることはなくなった。ダラダラと終わらない会議もなくなり、書類に印鑑が押されるのを待つ手間も無くなった。食事もショッピングも外出せず、家に届いたりと世の中の多くの煩わしさが消えた。

だが、本当に良いことばかりなのか?
入学したはずの大学の講義を、まだオンラインでしか受けたことのない新入生たちは、新しい友達もできず孤独感を味わっている。故郷を離れて1人暮らしを始めた学生ならなおさらだ。授業中に無駄話をすることも、廊下ですれ違うこともないので、新天地でなかなか友達や知り合いもいない状態で苦労をしているという話もよく聞いた。職場にしても、喫煙スペースや会議室からの帰り道、トイレなどでの雑談が消え去った。
デジタルは物事を効率化する。効率化するということは、何かを省くことだ。だが、省かれているものが、その時点の技術レベルや人類の経験値で決まる。それが本当にいらないのかは後になってからわかる。
かつて「高音質」で「聞こえなかった音も聞こえる」と言われていたCD(コンパクトディスク)は、後に「実は、それほど高音質ではなかった」とさらに高音質なディスクが出てきたり、アナログ映像と異なり「髪の毛一本一本まで見える」と称えられたハイビジョン映像が、今日では4Kや8Kと比べて臨場感が足りない映像の例に使われたりという、後になってそれまでの常識にまでアップデートが掛かるのがデジタルの世界だ。2018年に公開された高解像度な8K版「2001年宇宙の旅」が、実は50年も前のアナログ技術、70mmのフィルムを修復して製作されたといったことを聞くと「それじゃあ、これまでのハイビジョンや4Kは、なんだったんだ」という気にすらなってくる。

数値的な比較はできず定性的な評価になるが、コロナ禍で広まったリモート会議にしても、話した後の人々の反応や、テンポの良い掛け合い、隣の人とのヒソヒソ話や、同じ部屋で同じ空気を体感している感覚、そして会議後の帰り道での雑談といった、「効率化」され消えてしまったものにも大きな価値があった、と多くの人々が気づき始めているのではないか。
もっともデジタルによる効率化は、COVID-19のパンデミックの有無に関わらず、我々の運命だった。コロナ禍の前、我々はIoT、センサー、ビッグデーター、AIによる急激な効率化の渦中にあった。ただ、それをおおごとにしなかったのは、多くの人がそれを「良い」ことだと信じていたからだろう。

だが、果たしてそうなのか?
世の中には「効率化がいい」と信じている人が多い。だが、あえて問いたい。そもそも何のための効率化なのか? Windows 95の登場とともに、世界中のオフィスにパソコンが広がって、「効率化」が進んだ時、私を含めたデジタル推進側の人間が口にしていたのが「効率化によって余った時間で、人々はよりクリエイティブな時間を過ごすことができる」というものだった。だが、本当にそれができたと実感できた人は果たしているだろうか。
パソコンによる効率化が進み、インターネットで世界がつながった後、実際に起きたことは「人々はさらに忙しくなる」だった。効率化によって、働く時間に比例して売り上げが伸びる時代になったが、それと同時に競争も激しくなった。非効率で仕事にも隙間だらけだった時代の方が、その隙間を使っていくらでもクリエイティブな活動ができた。隙間を水で埋めるように入り込んだ「効率化」は逆にクリエイティブになる機会を奪い、データに裏打ちされた「確かに売れる」けれど、どこかワクワクしない効率的な仕事を量産し始めた。
我々がこの四半世紀に体験したのはとんでもない変化だった。しかし、人々がそれを「渦中」といって恐れないのは、人々がそうした効率化の価値観の内側に閉じ込められているからだ。20世紀中頃に活躍した文明批評家、マーシャル・マクルーハンの言葉にこんなものがある。
「誰が水を発見したのか知らないが、魚でないことだけは分かる。」
まさにその状態だ。今、コロナ禍が、そんなデジタルによる「効率化」をさらに推し進める強力な追い風となっている。
水槽の外の視点を持つための方法がアートだ
AIを含めたデジタル技術による効率化が進む時代だからこそ、「人間っぽさ」が大事だとよく言われる。しかし、効率化された社会環境に囲まれている我々は、その中でどうやって、その「人間っぽさ」を獲得すればいいのだろう。
方法の1つは「旅」に出ることだと私は思っている。「旅」に出ると、自分を包んでいた環境、常識が剥がされる。それまでの自分の常識の延長線上にはなかった景色や建物、食べ物。それらに心を打たれる部分もあるが、同時にそれらに触れ、自分の心がどう動いたかで自分自身が持っている価値観を知ることもできる。自分がやってきた仕事に似たことも訪問先では違う形で実現していることがある。

人は一度、自分を包む環境の外に出ることによって、初めて自らを俯瞰し、その輪郭を知ることができる。旅人は、訪問先で未知の物事を発見するのと同時に、自分自身の新たな一面も発見している。そうやって人々は、それまでの閉じた飛び出した発想をするために必要な経験値を少しずつ積んでいく。旅先が、言葉も通じない「海外」となれば、積まれる経験もさらに大きなものとなる。
そして、もう1つの方法が「アート」に触れることだ。
もちろん、「アート」と言っても多種多様ですべてがそれに該当するとは限らない。だが多くのアーティストたちは、今の社会を突き動かしている資本主義の論理や、経済合理性といった枠組みの外側、つまり我々がいる水槽の外側で作られている。右肩上がりの業績を目指さないといけなかったり、競合や他部署を気にしながら自分の領分の中で仕事をしなければいけない縛られた人々たちとは異なり、アーティストたちは自分たちのルールで枠組みを作り、そこから自分たちのアングルで物事を見て表現する。
そうしたアーティストたちが提示した価値観と自分が持ち合わせていた価値観が交差したとき、そこに感情が発生する。時には喜びや笑い、時には不安、時には怒り、そして時には自分でもわからない感動や衝撃だったりする。すべての人が同じ感情を持つわけではない。でも、だからこそアートに触れることで人は自分自身を水槽の外側からみて、どういう価値観を持った人間だったのかを改めて知ることができる。
さて、前置きはこのぐらいにして、今後本連載では、私が実際にそんな視点で触れてきたオススメのアート作品や、そこで得たインスピレーションを「Artistic Inspiration」として紹介していきたいと思う。